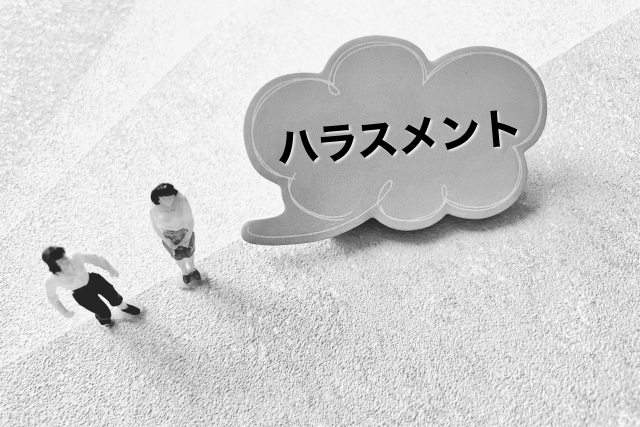職場や学校など、既成今日の社会においてセクハラ問題は常に調ほに上る問題の一つです。
この記事では、セクハラを行う人の特徸や背景にある心理、そしてそれが起こりやすい環境についても解説します。
前半では『セクハラをしやすい人に共通する8つの特徸』を、後半では『セクハラに自然に自分を誘う人の心理的背景3つ』を頂点的に解説しています。
記事を通じて、セクハラの本質を理解し、それから自分や近しい人を守るための知識を身につけることができるはずです。
セクハラ加害者に見られる8つの特徴
セクハラを行う人物には、共通する行動傾向がいくつか見られます。中でも、相手の立場や気持ちを無視した言動が目立ちます。
このような特徴を把握することで、早期の気づきや予防に役立てることができるでしょう。
セクハラ加害者によく見られる8つの特徴は次の通りです。
・相手の気持ちを想像しない
・嫌がっていても行動を改めない
・性に関する話をよく持ち出す
・身体に触れようとする
・下品なジョークを繰り返す
・性別による差別的発言が多い
・地位や権限を使って支配しようとする
・自分の行動を問題視しない
それぞれの行動について、詳しく見ていきましょう。
相手の気持ちを想像しない
セクハラをする人は、自分の言動が相手にどう影響するかを考えない傾向があります。
たとえば、次のような行動が見られます。
・個人的な話題を突然振る
・相手の表情や態度を気にせず話を続ける
・拒否されても気にしない
他人の感情に共感できないことは、無意識の加害行為につながりやすくなります。
嫌がっていても行動を改めない
相手が嫌がるサインを見せても、そのまま行動を続けてしまうのも特徴です。
例としては、
・相手が避けても身体接触を試みる
・話題を変えようとしても性的な話を続ける
・「冗談だ」と言い訳して繰り返す
こうした無視は、相手の尊厳を深く傷つける重大な問題です。
性に関する話をよく持ち出す
場の空気や関係性を考えず、性の話題を頻繁に持ち出すのも特徴です。
・相手の見た目について露骨に話す
・自分の性的経験を語る
・誰かのプライベートを茶化す
これらは聞いている人に強い不快感を与えます。
身体に触れようとする
セクハラ行為には、不必要な身体接触も含まれます。
・肩や腰を触る
・距離を詰めて話す
・髪や服に触れる
相手の同意なく触れることは、明確な侵害行為です。
下品なジョークを繰り返す
性的な内容を含む冗談を、不適切な場面で口にすることもよくあります。
・下ネタやダブルミーニング
・性的指向や性別をネタにする
・身体的特徴をからかう
「冗談だから」で済まされる問題ではありません。
性差別的な発言が多い
性別に基づく固定観念や偏見から、差別的な発言を繰り返すケースもあります。
・「女性は感情的だ」といった決めつけ
・役割を性別で限定する
・性別による能力差を強調する
これらは無意識のうちに他者を傷つけ、差別を助長します。
地位や権限を使って支配しようとする
役職や立場を利用して、相手にプレッシャーを与える言動も見られます。
・評価をちらつかせて要求をする
・断った場合の不利益をほのめかす
・親密さを強制する
これは権力の乱用であり、重大なハラスメントです。
自分の行動を問題視しない
セクハラをする人は、自分の言動を軽く受け止めがちです。
・「そんなつもりはなかった」と言い訳する
・「相手が神経質すぎる」と責める
・「昔は普通だった」と開き直る
自らを省みる姿勢がなければ、被害は繰り返されます。
セクハラは加害者が自覚を持たない限りなくならない問題です。自分の言動がどう受け取られるかを常に意識することが、健全な関係の第一歩となります。
セクハラを引き起こす心理的な背景3つ

セクハラ行為を行う人には、自己本位な考え方をしていたり、相手の感情を汲み取る力が弱かったりするなど、共通する心理的な傾向があります。
こうした背景を知ることで、セクハラの予防や抑止につながる対応策を考えることが可能になります。
セクハラ加害者の心理には、以下の3つの要因が関係していることが多いです。
・自己中心的な思考傾向が強い
・相手の気持ちを汲み取る力が乏しい
・過去に行為が許されてきた経験がある
それぞれの要因について、詳しく見ていきましょう。
自己中心的な思考傾向が強い
セクハラを行う人の中には、自分の考えや欲求を最優先する傾向が強く見られます。
つまり、相手の気持ちや立場に関心を持たず、自分の満足感や関心を満たすことに重きを置いているのです。
このような考え方の例には、
・自分は特別だから何をしても許されると思い込む
・相手が嫌がっていても気に留めない
・「悪気はないから問題ない」と思い込む
といったものがあります。
こうした価値観が根底にあると、相手への配慮や共感の欠如につながり、結果としてハラスメントが常態化しやすくなります。
相手の気持ちを汲み取る力が乏しい
セクハラをする人の中には、相手の感情を読み取ることが苦手な人が少なくありません。
そのため、相手が不快に感じているサインや拒否の意志を見逃し、無意識のうちに相手を傷つけてしまうことがあります。
例えば、
・相手が困惑した表情をしても気づかない
・場の空気を読まずに不適切な話題を出す
・断られても冗談と受け取り、繰り返す
といった行動が挙げられます。
共感力や社会的感受性が低い場合、問題行動の深刻さに気づかないまま繰り返してしまうリスクが高まります。
過去に行為が許されてきた経験がある
過去にセクハラまがいの行為をしても周囲が見て見ぬふりをしたり、組織が厳正な対応を取らなかった経験が、加害者の行動を助長することがあります。
たとえば、
・軽口のような性的発言に周囲が笑って受け流した
・部下への過剰な接触を誰も指摘しなかった
・会社として明確な制裁措置がなかった
といった環境があると、「これくらいは許される」と誤った安心感を持ってしまうのです。
このような場合、本人が自分の行動を正当化しやすくなり、繰り返しにつながります。
組織としてハラスメントに対して明確な姿勢を示し、一貫した対応を徹底することが重要です。
セクハラが起こりやすい職場の環境4つ
セクハラは、性別による権力の偏りが大きいなど特定の職場環境で発生しやすいとされます。
これらの環境要因をしっかりと把握し改善を図ることで、セクハラ予防に繋がると考えられます。
セクハラが起こりやすい職場環境には、以下の4つの紹介がされます。
・性別による権力の偏りが大きい
・コミュニケーションが閉鎖的
・ハラスメント対策が不十分
・飲み会や宴会が多い
これらは、セクハラを生み出しやすい土壌を作り出す要因でもあります。
それぞれの環境について、詳しく見ていきましょう。
性別による権力の偏りが大きい
性別による権力の偏りが昼どる職場では、地位や発言力の差を胸に、不適切な行為が生じやすくなります。
例えば
・男性の管理職が多く女性が補助的な仕事に固定されている
・昇進に性別の偏りがある
・女性が少数になっている組織
これらは、強い側の言勢が不適切な行為を正当化する土壌となります。
能力や成果による公平な評価の実現は、環境改善の要です。
コミュニケーションが閉鎖的
オープンな意見出しや問題提起がしにくい環境も、セクハラを添えやすくします。
たとえば
・上下関係で意見を言いにくい
・話し合う場がない
・悪い意見を指摘する人が際立つ
これらは、被害者が声を上げにくい空気を生み、問題を長期化させる原因になります。
ハラスメント対策が不十分
ハラスメント対策が不十分な職場は、セクハラを湧況させるとして危険です。
例えば
・教育や研修がない
・相談窓口がない、あっても知られていない
・問題発生後も是正策があいまい
これは、組織としてセクハラを認識しようとしない姿勢の表れでもあり、被害者が助けを求めない原因となります。
明確な対策方針の設定と、行動に縞り立てる実行力が求められます。
飲み会や宴会が多い
飲み会や宴会の常慎的な開催も、セクハラを展開させる要因になりえます。
例えば
・常に業務終了後の飲み会がある
・参加が際立になっており抵抗しづらい
・さけの役がらな状況に常識がありません
これは、自由な参加を集団のプレッシャーが削いでしまうことにも繋がります。
その結果、飲酒の加算でいつもはいえない言動をしてしまい、セクハラを展開させる原因となることも。
プライベートと業務の境界を明確にし、自由に選択できる環境を作ることが大切です。
セクハラ被害を受けたときにとるべき4つの実務的対応
セクハラの被害を受けた場合、明確に不快を表し、適切な行動を起こすことが重要です。
これによって被害の拡大を防ぐと同時に、問題の添う解決につながる可能性が高まります。
セクハラ被害時にとるべき4つのステップは以下の通りです。
・明確に拒否を示す
・上司や信頼できる人に相談する
・証拠を集める
・報道が難しい場合は法的手段も検討
これらの対応を絞らず実行することで、被害者の立場を守りながら問題を前向きに解決する道を開くことができます。
明確に拒否を示す
被害を受けたら、まず初めにはっきりと拒否の意思を示すことが大切です。
例:
・「それは不適切な言動です」と直接言う
・「そういう行為はやめてください」と明示
・表情や姿勢で不快を示す
このような対応は、効果的な警告となる上、後日の対応の資料にもなります。
信頼できる人へ相談する
一人で抱えこまず、上司や信頼できる人へ相談することは、問題を共有し経営側の対応を促すためにも有効です。
相談時のポイント:
・証拠を描けなくても、フェアにならないように事実を精精と説明
・自分が受けた心足や影響を伝える
・期待する支援内容を明らかにする
対応の領域を整備すると同時に、「対策を求める」という立場を明確にすることで、グズグずに見あわせを避けられます。
証拠を集める
問題を勘計するためには、可能な範囲で証拠を集めることが有效です。
例:
・日時、場所、行動の詳細を記録
・メールやメッセージなどは占有、スクショの保存
・目撃者がいれば名前や編成で記録
証拠は、後編の法的手続きや組織の返信において重要な基礎になります。
法的手段を検討する
続いて問題が改善されない場合や、内部での解決が難しい場合は、外部の法的手段を検討することも選択肢の一つです。
・従業の得意分野である律師へ相談
・労働局への訴え出や、民事訴訟も検討
・相談にあたっての証拠整備
法的手段を検討する場合は一人で抱えこまず、適切な支援を求める勉強性が問題解決の根底となります。
それに加えて組織側は被害者が安心して相談できる環境を用意することが不可欠です。